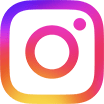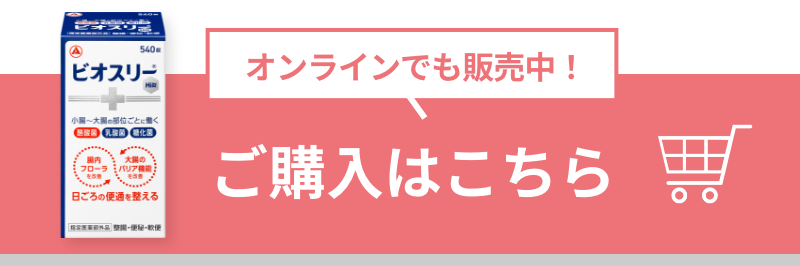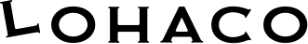更新日:2025年7月30日
妊婦が便秘になる原因とは?妊娠中の便秘対策についても紹介
監修:内藤 裕二 先生(京都府立医科大学大学院 医学研究科 教授/一般社団法人 日本ガットフレイル会議 理事長/日本潰瘍学会理事長/日本酸化ストレス学会副理事長)

INDEX
便秘に悩む妊婦の方は多いのではないでしょうか。妊娠中は、ホルモンバランスや生活習慣の変化、ストレスなど、さまざまな原因が重なり便秘になりやすいといわれています。便秘を我慢したままでいると、妊娠が進むにつれてさらにお腹が張り、苦しく感じてしまうことも。ここでは、妊婦が便秘になる原因や、自分でできる妊娠中の便秘対策について紹介していきます。
便秘の一般的な原因とは
便秘の種類ごとの原因
まずは、妊娠しているときに限らず、普段から起こることのある便秘の一般的な原因について解説します。
便秘は、その原因によって大きく2つに分けられます。1つは、大腸や小腸そのものの機能に原因があり引き起こされる便秘症で、「一次性便秘症」と呼ばれています。これらは食物繊維の摂取量不足や、いきむ際に使う筋肉の筋力低下、消化管の運動障害などが要因として挙げられます。
もう1つは、薬の服用や疾患が原因となり引き起こされる便秘症で、「二次性便秘症」と呼ばれています。これらは抗うつ剤などの服用による副作用、糖尿病などの基礎疾患、大腸がんなどによる腸管の狭窄(何らかの原因により形状が狭くなること)が要因として挙げられます。
便秘には、食生活はもちろん加齢や運動不足、ストレス、女性の生理周期などさまざまな要因が関わっているため、生活習慣を見直して腸内フローラのバランスを整えることが大切です。
・腸内フローラとは
腸内フローラとは、私たちの腸内に棲む約1,000種類、100兆個の腸内細菌の集まりのことです。腸内細菌には、体に良い影響を与える「善玉菌(有用菌)」(※以下、善玉菌)と、悪い影響を与える「悪玉菌(有害菌)」(※以下、悪玉菌)、そして善玉菌と悪玉菌のうち、どちらか優勢な方と同じ働きをすることのある「日和見(ひよりみ)菌」の3種類に分けられます。これらの理想的なバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」で、どれか1つが増えすぎても腸内環境は安定しないといわれています。しかし最近の研究では、善玉菌とされていたものの中にも良い働きをする菌とそうでない菌がいたり、悪玉菌や日和見菌だと思われていたものの中にも良い働きをする菌がいたりすることがわかっています。さらに、バランスだけでなく、腸内細菌の多様性も重要とされています。
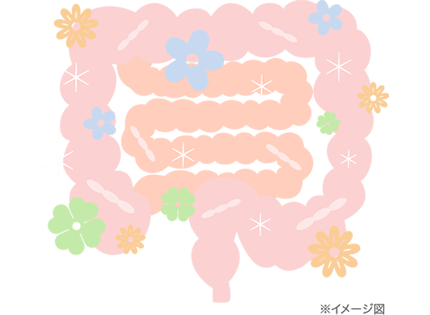
便秘を我慢すると悪循環に陥ることも
便秘になると、便が大腸を通過する時間が長くなります。大腸は食べ物の残りかすの中の水分を吸収して、便を適度な硬さにする役割があります。そのため、便が大腸の中に長く滞っていると、便の中の水分がより吸収されて、便はより硬くなってしまいます。
便が硬くなると肛門を傷つけてしまい、痔につながってしまうことも。さらに、その痔の痛みのために便意を我慢したりすると、ますます便秘がひどくなるという悪循環に陥ることも考えられます。
妊婦が便秘になりやすいのはなぜ?
ここまで便秘の一般的な原因について解説しましたが、妊娠中にはさまざまな要因が関係して便秘が起きやすくなります。報告によって差はありますが、妊婦の3~7割が便秘や排便困難感を訴えるといわれています。また、妊娠中の便秘により便が硬くなったり、硬い便を出そうとしていきむことで、痔を抱えてしまう女性も少なくありません。その影響が続いてしまい、出産後でも痔が治らないこともあるようです。
ここからは、妊娠中に便秘が起こりやすい原因を、より詳しく解説していきます。
プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌
妊娠が成立すると、女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)やプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増加します。このうちプロゲステロンは、妊娠を維持するように働いて、子宮内膜を厚くしたり、子宮の収縮を抑制したりします。
「子宮の収縮を抑制する」という作用は、「筋肉を緩ませる」ということです。この作用は子宮のみに限定されず、消化管にも及びます。つまり、消化管のぜん動運動(内容物を先へ送り出すための筋肉の収縮)を担っている筋肉も緩むため、妊娠中は腸にある便が滞りがちになり、便秘が起きやすくなるのです。
つわりによる食事量の減少や食事内容の変化
妊娠初期には、つわりの症状のために、いつものように食事を摂れなくなることが多いものです。食べる量が少なければ、当然ながら作られる便の量が少なくなるため、便秘の症状が現れます。また、食べる量が少なくなるだけでなく、栄養バランスが崩れてしまい、便秘解消に必要な栄養素である食物繊維などの摂取量が減ってしまうと、より便秘になりやすくなります。加えて、水分を十分摂取できていない場合には、便が硬くなってしまうため、それも便秘を悪化させる一因として挙げられます。
さらに、つわりの症状は、一般的に朝に強く現れやすい傾向があるといわれています。そのため、朝食の摂取量が減ってしまう傾向があります。しかし朝食は、体のリズムを整えて胃や腸を刺激し、排便を促す作用があります。そのため、つわりの症状のために朝食が十分に摂れないことも、妊娠中の便秘の大きな原因の1つとなります。
運動量の減少
普段の運動習慣も便秘に大きく関わっています。運動不足が続くと、腸の活動が鈍ってしまい、便秘が起こりやすくなるといわれています。妊娠中はつわりの症状や、赤ちゃんの成長とともに体が重くなることから、運動量が少なくなりがちです。また、切迫流産や切迫早産のリスクがある場合には、安静にすることが大切です。このようなことから、妊娠中は運動不足になりやすく、それに伴って便秘になる妊婦も少なくないようです。
ストレス
妊娠中はさまざまなことに気を遣う必要があるため、非妊娠時にはあまり感じることのないストレスを感じることも多々あるでしょう。
ストレスは、自律神経のバランスを乱す大きな原因の1つです。近年、腸と脳は、自律神経や情報伝達物質などを介して相互に密接な影響を及ぼし合っていることがわかってきていて、この関連は「脳腸相関」と呼ばれています。腸のぜん動運動にも自律神経が強く関わっているため、ストレスが原因となって便秘になることもあり、これもまた妊娠中に便秘がちになる理由の1つです。
子宮による腸の圧迫
お腹の中の赤ちゃんが成長してくると、大きくなった子宮に腸が圧迫されるという物理的な理由で、腸のぜん動運動が起こりにくくなり、便が腸の中を通過するのに時間がかかってしまいます。また、腸に血液を送っている血管が圧迫されて血流が悪くなりやすいことも、妊娠中の腸の働きの低下に関係している可能性があるといわれています。
妊婦が行いたい便秘対策
妊娠中の便秘対策は、基本的には妊娠していないときと大きく変わりません。食事内容の見直しやこまめな水分補給、適度な運動習慣などが重要です。ここでは基本的な便秘対策に加え、妊娠中だからこそ注意しておきたい点についても紹介していきます。
食事内容を見直す
・食物繊維を多く含む食べ物を摂取する
食物繊維は、胃や小腸で消化・吸収されずに大腸まで届き、水分を吸収して膨らむことで便を柔らかくしたり、かさを増やしたりすることで、便秘を予防・解消するように働きます。食物繊維は、野菜やきのこ、海藻などさまざまな食べ物に含まれていますが、多く含む食べ物の例としては、さつまいもやグリーンピース、昆布、ぶなしめじなどが挙げられます。他にも、大豆は水溶性成分(水に溶けやすい成分)が多く、腸内で発酵しやすい「高発酵性食物繊維」を含んでいるため、便秘の解消に期待できることが近年注目されています。
なお、野菜は食物繊維が豊富で、便秘対策に欠かせない食材ですが、妊娠中には食中毒などの感染症のリスクを抑えるために、なるべく火を通して食べたり、生野菜はしっかり水洗いして食べる方が好ましいとされています。そのため、手作りの野菜ジュースなどは避けたほうが良いでしょう。
・発酵食品を摂取する
腸の働きの多くには、腸の中に生息している腸内細菌が関わっています。実際に、腸内細菌の集まりである腸内フローラのバランスが崩れると、便秘をはじめとするさまざまな体の不調が起こりやすくなります。
発酵食品は、それ自体に腸内環境を改善するように働く善玉菌が含まれていたり、善玉菌のエサになったりして、腸内細菌のバランスを整えるように働きます。発酵食品の例としては、ヨーグルトやチーズ、納豆、みそ、漬物などが挙げられます。これらの食べ物の摂取も心がけると良いでしょう。ただし、妊娠中は免疫機能が低下しているため、食中毒などの感染症のリスクを避けるためには「生」や「無殺菌」の乳製品は避けたほうが良いでしょう。また、妊娠中の高血圧予防のために塩分を制限することも大切です。
こまめな水分補給を行う
食べた物が大腸に到達すると、そこでは食べた物の残りかすの水分が吸収されて、徐々に便の形が作られていきます。このとき、水分の摂取量が少ないと、便の水分量が減りすぎて必要以上に硬くなり、便秘につながってしまうことがあります。それを防ぐには、上述したような食物繊維や発酵食品などとともに、水分をこまめに摂取することで、柔らかく、大腸の中を通過しやすい便が作られます。毎朝の起床後に、コップ1杯の水を飲む習慣を付けると良いでしょう。
また妊娠中は、つわりにより食べたものを吐いてしまうこともあります。その際、水分も一緒に排出されてしまうため、より意識的に水分補給を行うようにしましょう。
適度に運動する
体を動かすと、腸を含め全身の血流が良くなります。また、運動は自律神経のバランスを整えるように働きます。これらの結果、運動によって腸のぜん動運動が改善し、便秘の予防・解消につながります。
ただし、妊娠成立後に運動を始める場合は、原則として妊娠 12 週以降で、妊娠経過に異常がないことを確認する必要があります。他にも、既往の妊娠に早産や反復する流産がないことや、単胎妊娠で胎児の発育に異常が認められないことも、確認すべき点として挙げられます。
運動の終了時期は、医師による診断のもとで特別な異常が認められない場合には特に制限されていませんが、妊娠中に運動をし過ぎると、お腹の中の赤ちゃんの負担となったり、思わぬ怪我が大事につながってしまうことも考えられるため、無理のない範囲で続けることが大切です。ゆっくりとした散歩やお腹に負担をかけない程度のストレッチ、スイミングなどが好ましいでしょう。
痔のケアをする
妊娠中には、便秘や下半身の血流低下のために、痔になりやすいといわれています。痔になると、その痛みのために排便をスムーズにしにくくなり、さらに便秘を悪化させてしまうこともあります。また、痔をそのまま放置してしまうと、妊娠中だけでなく産後にも続いてしまうことが考えられます。症状が悪化する前に医師に相談して、塗り薬や坐薬などを処方してもらうようにしましょう。
便秘には、妊婦でも服用できる整腸剤を活用する手も
ここまで解説したように、便秘の予防・解消には、食事内容の見直しや適度な運動などが大切です。しかし、妊娠中はつわりのために食事が進まなかったり、運動をすることが難しいということもあるでしょう。そのようなときには、妊婦でも服用できる整腸剤を活用するという手もあります。
便秘対策として腸内フローラのバランスを整えるには、善玉菌を増やすことが重要です。善玉菌の種類としては、乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌などがあります。これらのうち酪酸菌は、腸の中で酪酸を産生し、その酪酸が大腸のぜん動運動のエネルギー源として使われたり、腸内環境を整えたりする働きを持ちます。
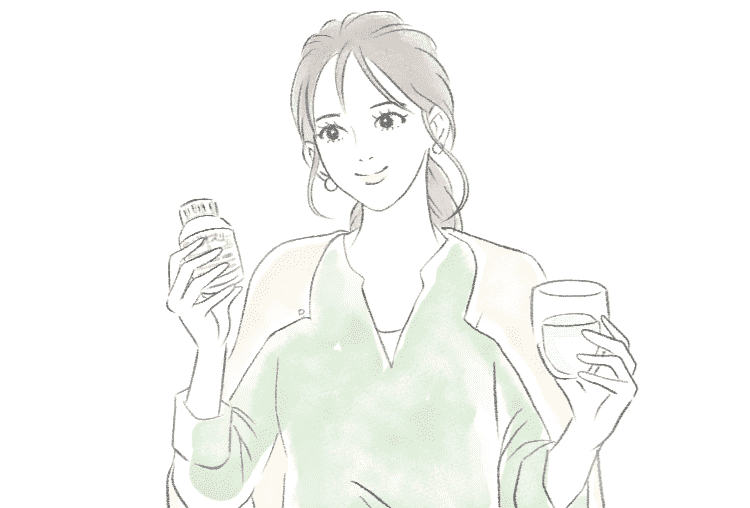
乳酸菌が含まれている食べ物はさまざまなものが挙げられますが、酪酸菌が含まれている食べ物はごく限られています。食べ物から摂取しにくい酪酸菌は、酪酸菌を配合した整腸剤を活用すると、手軽に摂取することができるため良いでしょう。購入の際には、薬剤師に妊娠中であることを伝えて相談してみましょう。
妊婦に起こりがちな便秘には、自分でできる対策を試してみよう
妊娠中には、ホルモンバランスや生活習慣の変化、新しい家族が増えることへの期待や不安によるストレスなど、さまざまな要因が織り交ざり、便秘を引き起こしやすいといわれています。便秘対策の方法は、妊娠中でもそうでない場合でも基本的には変わりません。しかし、つわりの症状のために食事を工夫したり、運動したりすることが難しい場合は、妊娠中でも服用できる整腸剤を活用してみるのも良いでしょう。自分でできる便秘対策を試してみて、それでも十分に改善しないときには、医療機関での診察を受けるようにしましょう。
- [参考文献]
-
- ・南江堂,「便通異常症診療ガイドライン2023慢性便秘症」,2023
- ・医学書院,「助産診断・技術学 2 1(妊娠期) 第4版」,2007
- ・メディックメディア,「病気がみえる 産科 第4版」,2018
- ・日本臨床スポーツ医学会 産婦人科部会,「妊婦スポーツの安全管理基準」,2005
PRODUCT ビオスリー製品情報
おなかの調子を整えるなら

 整腸(便通を整える)
整腸(便通を整える)
便秘・軟便・腹部膨満感