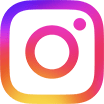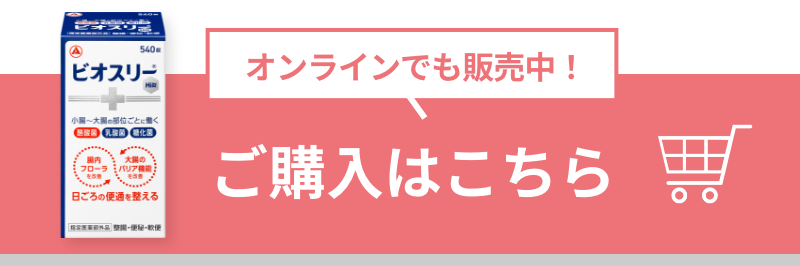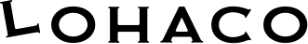更新日:2024年12月23日
レジスタントスターチとは?食物繊維としての働きや腸内環境に与える影響も解説
監修:内藤 裕二 先生(京都府立医科大学大学院 医学研究科 教授/一般社団法人 日本ガットフレイル会議 理事長/日本潰瘍学会理事長/日本酸化ストレス学会理事長)

INDEX
レジスタントスターチは「難消化性でんぷん」とも呼ばれ、小腸で消化・吸収されないでんぷんのことをいいます。従来、食物から吸収されたでんぷんはすべて、体のエネルギー源として利用されると考えられていましたが、レジスタントスターチは小腸で消化・吸収されず大腸まで届き、腸内環境に影響を与えることがわかってきました。今回は、そんなレジスタントスターチのメリットや働き、食物繊維とは違うのかなどの疑問について解説します。
レジスタントスターチとは
レジスタントスターチは、「健康な人の小腸において消化・吸収されることのないでんぷんおよびでんぷんの部分消化産物の総称」と定義されています。レジスタントスターチの「レジスタント(resistant)」は「抵抗力のある」という意味で、「スターチ(starch)」は「でんぷん」という意味。2つをあわせると、「抵抗力のあるでんぷん」という意味になります。この場合の抵抗力とは、消化酵素(消化液)に対する抵抗を指します。レジスタントスターチは、その特徴から「難消化性でんぷん」と呼ばれることもあります。
でんぷんは、糖が多数結合してできる「多糖類」に分類される炭水化物です。一般的にでんぷんを摂取すると、消化酵素によって細かく分解されてブドウ糖となり、小腸で吸収され、全身のエネルギー源として使われます。それに対してレジスタントスターチは、でんぷんの一種ではあるものの、小腸でほとんど消化・吸収されないという特徴があります。
レジスタントスターチの種類
レジスタントスターチは、その性質の違いによって以下の5種類に大別されます。種類により、多く含む食品も異なります。
<レジスタントスターチの種類、性質、食品例>
| 種類 | 性質 | 食品例 |
|---|---|---|
| RS-1 | 食品の細胞壁が硬いために、消化酵素が物理的に作用できないでんぷん | 全粒穀物、精製度の低い穀物、でんぷん密度の高い食品(パスタなど) |
| RS-2 |
|
|
| RS-3 | 加熱によっていったん糊化した後、冷却することで再結晶化され、消化酵素に対する耐性が生じたでんぷん。「老化でんぷん」ともいう | 加熱後に冷ました、老化でんぷんを含む食品(冷やご飯など) |
| RS-4 | 化学的な加工によって、消化酵素に対する耐性を高めたでんぷん | 加工食品(スナック菓子や菓子パン、冷凍食品など) |
| RS-5 | アミロースと脂肪の複合体となることで、消化酵素に対する耐性を持ったでんぷん | 油脂類を使って加工・調理されたでんぷんを含む食品 |
- *1 アミロース:でんぷんを構成する成分の1つ。「アミロペクチン」という成分とともに、穀物類に多く含まれている。
- *2 糊化(こか):糊のように弾力のある状態へ変化すること。
レジスタントスターチと食物繊維は何が違う?
食物繊維とは
消化酵素で消化されにくい栄養素として、食物繊維をイメージする方も多いのではないでしょうか。食物繊維の定義は国によって少しずつ異なりますが、主には「人の消化酵素で消化されない、食物中の難消化性炭水化物」といわれています。その働きとしては、唾液や胃液を含めた消化管内の水分を吸収し膨張することで空腹感を抑制したり、食べ物が胃から小腸へ移動するのを遅らせて、食後の急な血糖上昇を抑制したり、糖や脂肪の吸収を抑制したり、腸のぜん動運動(腸の内容物を先へ先へと運ぶための運動)を促して排便をスムーズにしたりといったことが挙げられます。
レジスタントスターチは食物繊維とは違う?
・レジスタントスターチは、食物繊維の一種として分類されている
以前、レジスタントスターチは食物繊維とは区別されていましたが、2018年以降、食物繊維の測定を国際基準に合わせるようになったことで、レジスタントスターチも食物繊維の一種として分類されるようになりました。
・レジスタントスターチの栄養素としての特徴
食物繊維の中でも、とくに腸内で発酵しやすく、「善玉菌(有用菌)」(※以下、善玉菌)のエサとなる食物繊維は「発酵性食物繊維」と呼ばれていて、健康にとってプラスに働く、重要性の高い食物繊維と考えられています。
レジスタントスターチは、発酵性食物繊維であり、その中でも腸内細菌により良く発酵される「高発酵性食物繊維」といわれています。
・食物繊維に分類される栄養素の構成成分の違い
食物繊維は、「難消化性炭水化物」といわれますが、その中でも分類によって構成成分に違いがあります。レジスタントスターチや難消化性デキストリンなどが「でんぷん性多糖類」であるのに対し、オリゴ糖やセルロースなどは「非でんぷん性多糖類」に分類されます。両者の大きな違いは、でんぷんであるか否かという点です。
でんぷんはブドウ糖を含んでいるため、エネルギー源になり得ます。ただし、レジスタントスターチや難消化性デキストリンなどは難消化性のでんぷんであるため、直接的なエネルギー源にはなりにくいのです。それに対して、オリゴ糖やセルロースなどはでんぷんではないため、エネルギー源となり得るブドウ糖を含んでいないという点に違いがあります。
なお、難消化性デキストリンは、トウモロコシやジャガイモなどの天然のでんぷんを加熱処理して人工的に作られた低分子量水溶性食物繊維のことであり、新しい測定法ではでんぷん性に分類される食物繊維の一種です。
レジスタントスターチが腸内環境に与える影響とは
善玉菌を増やす
レジスタントスターチは、腸内の善玉菌のエサとなり、善玉菌の増殖をサポートするように働きます。加えて、レジスタントスターチは大腸の下部(下行結腸)にまで届き、そこに棲みつく善玉菌のエサになるという特徴があります。
・腸内環境を左右する「腸内フローラ」の理想的なバランスとは
人間の腸内には、約1,000種類、100兆個の細菌が生息しているといわれ、そのような細菌の集まりのことを「腸内フローラ」と呼んでいます。腸内フローラは上述の「善玉菌」、「悪玉菌(有害菌)」(※以下、悪玉菌)、またこれら2つのうちどちらにも属さない「日和見(ひよりみ)菌」の3つで構成されています。日和見菌の中には、善玉菌・悪玉菌のどちらかが優勢になると、優勢な方と同じ働きをする菌もいます。
腸内フローラの理想的なバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」といわれていて、腸内環境の維持や改善のためには、このバランスを崩さないことが重要です。基本的には善玉菌を積極的に摂取し、悪玉菌よりも優勢な状態を保つことが大切です。
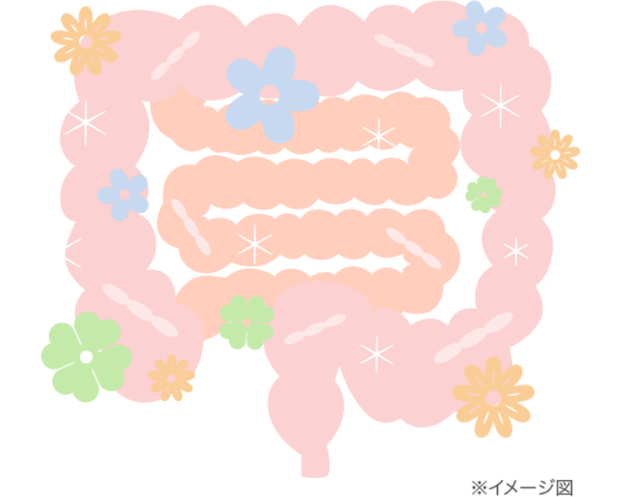
短鎖脂肪酸を産生する
前述のとおり、レジスタントスターチは発酵性食物繊維の中でも、腸内細菌によって良く発酵される「高発酵性食物繊維」といわれています。腸内細菌による発酵を受けると、酪酸や酢酸、プロピオン酸などの短鎖脂肪酸が産生されますが、レジスタントスターチはとくに酪酸の産生が多いといわれています。短鎖脂肪酸が産生されることで、以下に解説するような健康上のメリットを生むといわれています。
・悪玉菌の増殖を抑える
短鎖脂肪酸の産生によって腸の中が弱酸性の状態になり、悪玉菌の増殖を抑制するように働きます。その結果、善玉菌が優勢となり腸内環境が整います。
・腸の粘膜のエネルギー源になる
短鎖脂肪酸、とくに酪酸の多くは、大腸上皮細胞のエネルギー源としても使われます。そこから得たエネルギーは、大腸のぜん動運動などに利用され、大腸を動かすことで便通を促します。
・腸のバリア機能や免疫機能にもかかわる
ウイルスや細菌などの異物に対抗するための免疫細胞の約7割は腸管にあり、腸は免疫機能にとって重要な臓器といわれています。
短鎖脂肪酸のうちの酪酸は、まず、大腸のバリア機能に必要とされる粘液分泌を高めて、異物が体内に侵入するのを防ぐように働きます。また、異物に対する抗体の1つで、体内に最も多く存在している「免疫グロブリンA(IgA)」の作用を高めるようにも働き、この働きも感染症のリスク抑制につながると考えられます。
・その他
短鎖脂肪酸は上記の他にも、糖や脂質の代謝を改善するように働いたり、微量栄養素であるミネラルの吸収を高めたり、炎症を抑制したりといった、健康の維持・増進に役立つさまざまなメリットがあることがわかっています。
レジスタントスターチを摂る際の注意点
レジスタントスターチを摂るなら…ご飯は炊き立てよりも冷やご飯
レジスタントスターチは特殊な栄養素ではなく、イモや豆、米、麺などに含まれています。しかし、レジスタントスターチを多く摂ることを目的として、でんぷんが含まれる食品を多く食べようとすると、エネルギー過多になってしまいかねません。そのため、効率良くレジスタントスターチを摂るための工夫が必要です。
そこで注目したいのが、上記のレジスタントスターチの種類のうちの「RS-3」を意識して摂取する方法です。このときに重要となるのが、食べるときの食品の温度です。RS-3は「加熱によっていったん糊化した後、冷却することで再結晶化され、消化酵素に対する耐性が生じたでんぷん」です。わかりやすく表現すると、温かいご飯(お米)は粘りがありますが、冷めたご飯は粘りが減ります。冷まされたことでそのように変化したでんぷんは、消化酵素が作用しにくい状態に変化しているということです。そのため、レジスタントスターチの働きを期待する場合、ご飯は炊き立てよりも冷やご飯がおすすめです。
このように、レジスタントスターチの含有量は食べ方で大きく異なり、基本的には調理のための加熱後に冷ますことで増加します。この特徴を利用することで、でんぷんが含まれる食品の摂取量はあまり増やさずに、レジスタントスターチの摂取量を増やすことが期待できます。
・ご飯の冷まし方
冷やご飯のように、加熱調理後に冷却することでできるレジスタントスターチの含有量は、加熱に用いる調理器具や加熱方法、加熱温度によって異なります。手軽さと衛生面を考えた場合、加熱調理後に冷蔵庫に入れて冷やす、または、常温でしばらく置いて冷ますという方法が良いでしょう。
・再加熱は避ける
レジスタントスターチは、60℃程度に再加熱すると、最初に加熱したときほどではないですが、多くは元のでんぷんに戻ってしまいます。そのため、おにぎりやお弁当なども、電子レンジで温めずに冷めた状態で食べることで、レジスタントスターチを効率良く摂取できるでしょう。
他の食品とのバランスを考慮して摂取する
レジスタントスターチには多くの健康上のメリットがありますが、摂りすぎると良くない影響が生じることもあります。例えば、お腹が張ったり、下痢をしやすくなったりすることが知られています。これは、レジスタントスターチの働きが強く表れ過ぎた結果ともいえます。
レジスタントスターチのメリットの多くは、腸内で腸内細菌による発酵を受けることで発揮されますが、発酵にはガスの発生を伴うため、お腹が張るという症状につながることがあります。また、レジスタントスターチの摂取により大腸のぜん動運動が促進されるという働きが過剰になった場合に、下痢が生じることがあるといわれています。
レジスタントスターチに限らず、栄養素は摂れば摂るほどより良い効果が期待できるのではなく、必要な栄養素をバランス良く摂ることが大切です。食生活にレジスタントスターチを取り入れる場合は、少しずつ摂取量を増やしたり、他の食品とのバランスを見て摂取したりすると良いでしょう。
・ビタミンB12の不足にも気をつけるように
レジスタントスターチを大量に摂取した場合、大腸で「プロピオン酸」という短鎖脂肪酸が作られる流れの中で、「コハク酸」という腸内で炎症を引き起こすことがある物質が生成されます。このコハク酸をプロピオン酸に変える過程では、ビタミンB12が補酵素(酵素の働きを補う物質)として必要とされます。そのため、レジスタントスターチを摂取するときは、ビタミンB12の不足に注意したほうが良いといわれています。
レジスタントスターチで健やかな腸内環境を目指そう
レジスタントスターチはでんぷんの一種でありながらも、小腸で消化・吸収されないという特徴を持つ栄養素。摂取することで、善玉菌を増やしたり短鎖脂肪酸を産生したりするという働きから、腸内環境に影響を与えることもわかっています。また、この腸内環境を整えることが体全体の健康にもつながります。栄養素はバランス良く摂ることが大切なので、摂り過ぎには注意しつつ、お腹の調子で悩んでいる方はレジスタントスターチの摂取を心がけてみてはいかがでしょうか。
- [参考文献]
-
- ・日経BP「健康の土台をつくる 腸内細菌の科学」,2024,内藤裕二
- ・あさ出版「酪酸菌を増やせば健康・長寿になれる」,2022,内藤裕二
- ・文響社「腸すごい!医学部教授が教える最高の強化法大全」,2022,内藤裕二,小林弘幸, 中島淳
- ・日本家政学会誌 Vol. 65 No. 4 197 ~ 202(2014)「レジスタントスターチの開発」
- ・生物工学会誌 第102巻 第2号 81(2024)「レジスタントスターチとは?」
PRODUCT ビオスリー製品情報
おなかの調子を整えるなら

 整腸(便通を整える)
整腸(便通を整える)
便秘・軟便・腹部膨満感